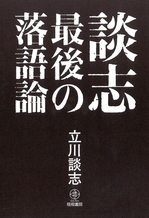完全書き下ろし「談志 最後の三部作」
1965年、談志29歳、『現代落語論』を上梓、ベストセラーとなる。
1985年、談志49歳、『あなたも落語家になれる』を上梓、「落語とは人間の業の肯定である」という名言を残す。
そして2009年、談志73歳、落語人生の集大成を三部作に込める――。
[第一弾] [第二弾] [第三弾]
2009年11月16日発売 2010年4月19日発売 2010年冬(予定)
[第一弾] 談志 最後の落語論 (四六判・上製、232ページ、定価:税込1890円) 落語とは何か。人間の業とは何か。名人とはだれか。客とはだれか。 進化した談志の落語論・落語家論の集大成です。 《目次》 第一章 落語、この素晴らしきもの 第二章 「自我」は「非常識」をも肯定する 第三章 〝それ〟を落語家が捨てるのか 第四章 そして、三語楼へとたどりつく 第五章 芸は、客のために演るものなのか 《本文のフレーズ》 ●人間というものの業、知性でも理性でもどうにもならないもの、 世間では〝よくない〟といわれているもの。 それらを肯定し、寄席という空間で演じられてきたのが落語である。
●「文明」とは、その時代々々の最先端であり、より速く、より多くを求めるもので、
それに取り残されたモノに光を当てたものを「文化」と称(い)う。 文明は、文化を守る義務がある。
●落語とは、非常識の肯定である。
●人間には良心も、正義も、愛もありゃしない。
(中略)〝そうさァ、そうよ、ムリだよォ。人間、セコいんだよォ〟と、落語は語ってくれる。 世の常識に組み込まれ、〝よし〟とされ、それを「出世」と称している奴なんざァ、 腹からバカにしてる。
●金で解決できるものと、「品(ひん)」とは別のものだ。
(中略)件で解決している品の悪い奴を笑っ知うのが落語というこった。 [第二弾] 談志 最後の根多帳 (四六判・上製、304ページ+巻頭カラー口絵8p、定価:税込2205円) 談志落語の創作プロセス、ネタ選びの基準を解説。 また、名演とされる近年の「伝説の高座」を活字で再現。 さらに、巻頭のカラー口絵には未公開の高座写真、巻末には200を超える談志のネタ一覧を収載。 「談志落語」の粋を凝縮した、ファン垂涎の一冊です。 《目次》 第一部 談志の根多論 第一章 直さずにはいられない 第二章 直した落語、作った落語 第三章 〝演らない〟にも訳がある 第二部 談志の落語 最近版 粗忽長屋(2007年、よみうりホール) 鉄拐(2007年、ミッドランドホール) 居残り佐平次(2004年、町田市民ホール) 芝浜(2007年、よみうりホール) 二人旅(2009年、よみうりホール) 落語チャンチャカチャン(2004年、横浜にぎわい座) 付録 談志の根多帳 談志の落語が読める本、聴けるCD、観られるDVDリスト付き 《本文のフレーズ》 ●常識に飽き、非常識に憧れ、そこからも抜けた『芝浜』『鉄拐』『二人旅』等々。 談志(わたし)ほど落語に深く興味を持った者は、過去一人も居るまい。 それを示した一つが、この「芸論」でもある。 ●江戸時代の匂い、江戸っ子の了見、寄席の雰囲気。これらがあわさって、江戸の風となる。 ●面白くない噺、受けない噺も、覚えないよりは覚えたほうがよい。 ●よくできた古典落語は、ほとんどそのまま演っている。 一例を挙げれば『明烏』であり、これは文楽師匠の『明烏』が染みついている。 これはそのまま、とっておきたい形である。 ●女であろうが、男であろうが、年寄りであろうが、子供であろうが、 また与太郎であろうが、猫であろうが、 談志の落語に登場するキャラクターは全て、談志(わたし)の分身といえる。 ●当然のことながら、人情噺は嫌いである。いくつか演っているが、すべて直している。 (中略)バカみたいに単純な勧善懲悪も嫌いである。 落語の中にも『水戸黄門』のようなつまらない噺が横溢していてね......。 ●まさに一期一会、同じ空間を共有した者でなければ判らないだろう。 もっと言うと、落語のダストの中にいる者でしか、 談志と同じ感動は味わえなかったかもしれない。